日々の生活に役立つ知識を身につけるために始めた「週1冊読書」。
本で学んだ知識を活かしていくためには、実践あるのみ。
そこで、毎週1冊の本を読んで、実際にやってみたことをご紹介していきます。
読んだ本
今回読んだ本は、横山 光昭さん・桜沢 エリカさんの著書『貯める達人使う達人が教える お金に好かれる人のルール!』
1万人以上の赤字家計を再生してきた 貯める達人 横山さんと、貯金がなくても楽しそうに生きる 使う達人 桜沢さん。
この本では、そんな2人の人生を楽しむためのお金との上手な付き合い方が紹介されていました。
その中で、私が実際にやってみたことや、既にやっていて効果を実感していることを、厳選して3つご紹介します。
① コンビニや100均に立ち寄らない
コンビニは「欲しいものがあって行く」のではなくて、欲しいものがなくても「何かないかな」という目線で訪れて、適当に買うことが多いです。
気分転換の意味で立ち寄り、それほど欲しくなくても何かを買って帰る。
気持ちを変えるためにお金を使うというのはもったいないです。
コンビニで毎日ちょこちょこと買ってスッキリした気になるのなら、それを少しガマンして、もう少し大きいものを買う。
そのほうが、スッキリする度合いが違います。
コンビニに限らず、100円ショップなんかも同様。
欲しいものがなくても、なにか買いたくなる。
ついなにかを買わなければいけない気になってしまいます。
「こんなに買って1,000円いかないなんて…」という気持ちになったりしますが、それに果たして意味があるのかどうか。
そういうところで小さなお金を使って、一瞬の「スッキリ」を楽しむよりは、高くても長く使えて、ずっとかわいがれるものにお金を使ったほうがいいです。
私もコンビニや100均には目的がない時は立ち寄らないようにしています。
買い物に行くのは、買いたい物がはっきり決まっている時だけで、月1回以下。
事前に買い物リストを作成し、リストにある物だけを購入。
リストにない物で欲しくなった物は、その場では買わずにリストに追加して、次回の買い物まで考えるようにしています。
コンビニや100均に行く回数を減らしたことで無駄な出費が減り、自分の好きなことにお金を使えるようになりました。
② 普段と「ハレの日」の予算を決める
1回の食事にざっくりとした予算があるという横山さん。
たとえば、お寿司ならだいたいひとり○○円くらいまで、イタリアンなら○○円、お酒を飲むなら○○円くらい、と頭の中にとどめる。
そのほか、普段の食事なら○○円、ちょっといい時にはこのくらいまで、なにかの記念日などのいわゆる「ハレの日」にはここまで、とランクごとの金額が頭の中で決まっているそうです。
それを超えると、なんだか心が痛くなる。
たとえ、食事がおいしかったとしても、味よりも金額がつい気になってしまって、なんとなくイヤな気分になります。
お世話になっている誰かのためにお金を出すのはまったく問題がない。
でも、「この食事には、このくらいの金額までしか出したくない」という基準があるので、予算以上のものを出すのに抵抗があります。
お金が減ってしまうことに対する嫌悪感というよりも、お金を必要以上に使うことに対する嫌悪感なのかもしれません。
私も家族3人で外食するときに、普段と「ハレの日」で予算をランク分けして決めています。
普段の外食は、月末のやりくり費の残額が上限。
「ハレの日」は、1人8,000円くらいまでで、合計25,000円が上限。
大体の予算を決めていることで、お金を必要以上に使ってしまうことがなくなりました。
また、普段の外食は、毎月使うやりくり費から出していますが、「ハレの日」は、年に数回使う特別費から支出。
予算の出どころを分けることで、「ハレの日」でも心置きなくお金を使えるようになりました。
③ お金以上に大切なものを優先する
お金第一で無理したり、それが苦痛になるようなことは絶対に避けるべきです。
貯金はつくるべきですが、楽しみも何もなく、ただただ苦しい思いをしてまで、というところまではしなくてもいい。
ただ「節約」だけではなく、いろいろなことにお金を出して経験する、ということも必要です。
そもそも、決してお金が一番ではありません。
仕事だったり、家族だったり、趣味だったり、休みだったり…お金以上に大切なものがあるはずなので、それらが優先されるべきです。
お金は将来に向けての支えになるものですから、管理する必要はあるでしょう。
けれど、なによりも最優先して、ガマンして、あらゆるものを切り捨ててまで貯めるものではありません。
私は、貯金とは別に家族へのプレゼントや自分へのご褒美に使うお金も貯めるようにしています。
通常の貯金と分けて管理することで、貯金が減ってしまうストレスを抱えずにお金を使うことができる。
自由に使うことができるお金があることで、時には息抜きをしながら貯金を頑張ることにもつながっています。
おわりに
その他にも参考になる方法がたくさん紹介されている、こちらの本。
気になった方は、ぜひ読んでみてくださいね!
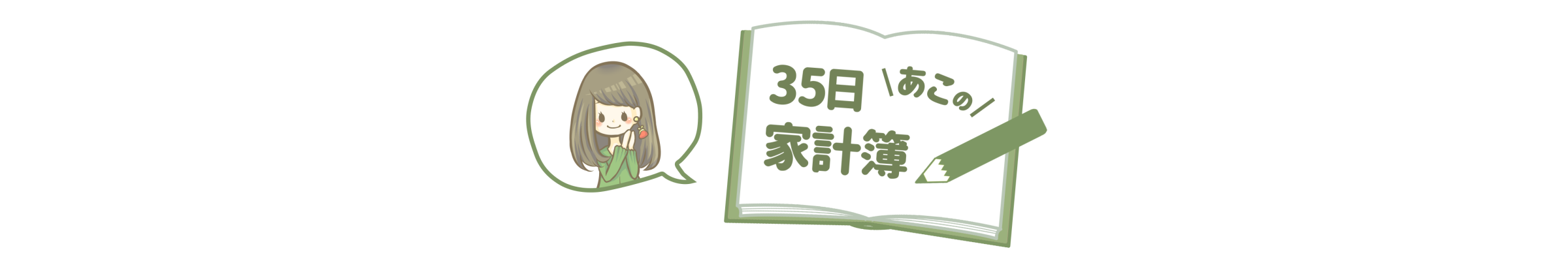
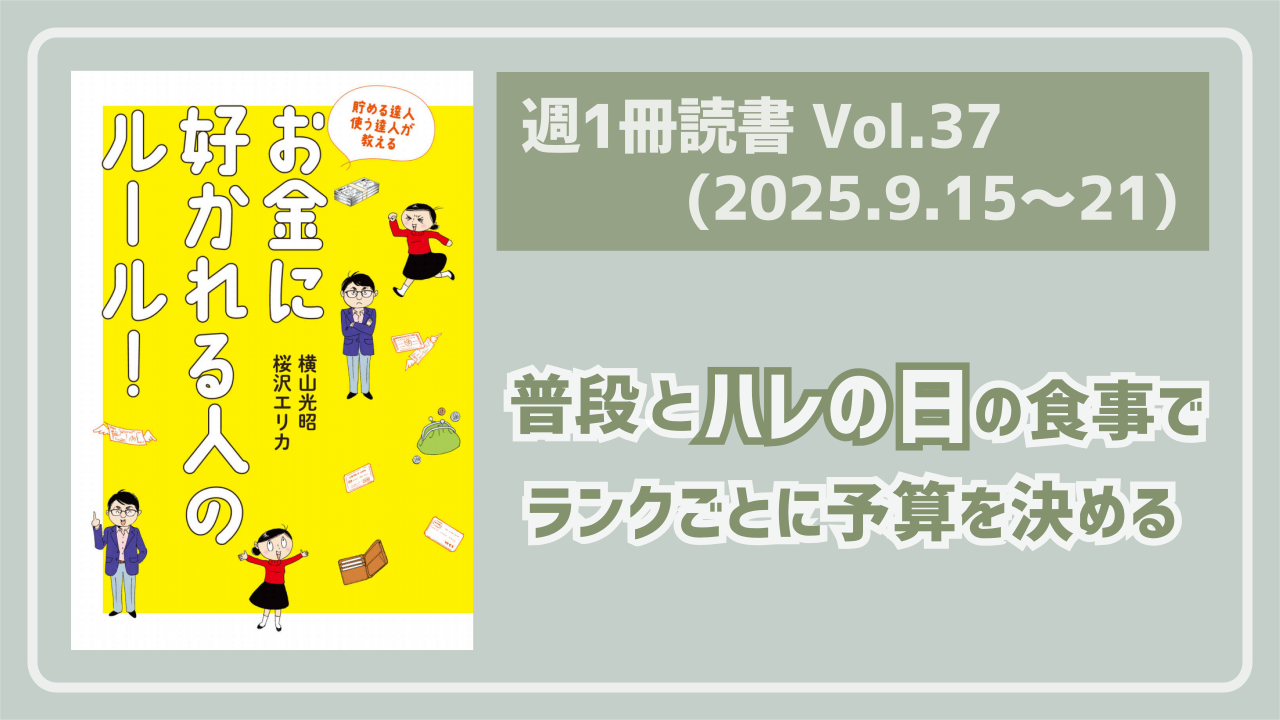
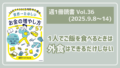

コメント