日々の生活に役立つ知識を身につけるために始めた「週1冊読書」。
本で学んだ知識を活かしていくためには、実践あるのみ。
そこで、毎週1冊の本を読んで、実際にやってみたことをご紹介していきます。
読んだ本
今回読んだ本は、えまさんの著書『忙しい人ほどマネしてほしい お金が増える暮らしのルール』。
育児をしながらでも自己流投資歴10年で600万円増やしたという著者のえまさん。
この本では、そんなえまさんが10年かかって辿り着いた「資産形成」と「節約」のバランスのとれた リスクの少ない投資方法が紹介されていました。
その中で、私が実際にやってみたことや、既にやっていて効果を実感していることを、厳選して3つご紹介します。
① 先取り貯蓄で投資資金を作る
「投資を始めたい。でも資金がない」という人は、まずはお金が増える仕組みを作ることが大切です。
「お金が余ったら貯蓄する」では、いつまでたっても貯まらないので、先取り貯蓄でお金を貯めているというえまさん。
先取り貯蓄なら、もともと「ないもの」として生活をするので、手持ちのお金の中で「本当に必要かどうか」の優先順位をつけて、支出を慎重に考えるクセがついたそうです。
NISAなどの「先取り貯蓄」をする一方で、えまさんの給料と旦那さんの残業代はなかったものとして、こちらも「先取り貯蓄」。
生活費は旦那さんの基本給だけでやりくりし、先取り貯蓄がある程度貯まったら、投資へ回すという仕組みができました。
私も、先取り貯蓄で投資資金を作っています。
時給制で働いているので、一番勤務日数が少ない月の残業代なしの給料で毎月やりくり。
給料から毎月5万円をNISAで先取り貯蓄し、残りのお金で生活しています。
勤務日数が多かったり残業代が出て多かった分の給料は、老後貯金と生活防衛貯金に振り分け。
老後貯金は、長期的に使う予定がないため、投資に使ってもOK。
生活防衛貯金は、失業などの万が一の時に備えるものなので、投資には使ってはいけないお金です。
このような仕組みを作ったことで、少ない収入でも生活を守りながら投資にお金を回すことができています。
②「特別費」を用意する
特別費とは、年に1回あるいは数回、まとまった支出が予想されるもの。
固定資産税や家族の誕生日のプレゼント代、帰省費用などが特別費にあたります。
特別費の予算をとっておかないと、月によっては赤字になってしまう。
赤字転落すると家計管理の挫折の原因にもなります。
1年間の特別費予算を生活費とは別枠で確保しているというえまさん。
かなりの金額になるので、ボーナスを特別費に回しているそうです。
私は、ボーナスがないので、35日家計簿や小銭貯金でボーナスを作っています。
自分で作ったボーナスは、生活費とは分けて特別費の口座で管理。
生活費でやりくりできない大きな出費は、特別費から出すようにしています。
特別費の予算を別枠で確保することで、毎月の生活費の赤字を防げる。
毎月黒字でやりくりできるようになり、モチベーションを保ちながら家計管理を続けることができています。
③ ほったからし投資
子どもの教育費や老後資金など、お金を使うまでに時間的余裕があるものは、投資で運用しているというえまさん。
万が一、お金が必要になったら、引き出しはいつでもできます。
税金がお得な「NISA」の枠内で投資信託の積み立て購入を設定し、その後はほったからし。
育児と仕事で忙しいので、月に1回しか投資の状況を確認しません。
また、投資で出た利益は、生活費に反映させるのではなく、再投資に回して将来の利益に期待しているそうです。
私も、NISAで毎月投資信託を積み立て購入し、ほったからしにしています。
再投資型で積み立てているので、投資で得た利益は自動で再投資に回してくれる。
投資状況の確認も数ヶ月に1回しているだけなので、手間をかけずに投資を続けることができています。
おわりに
その他にも参考になる方法がたくさん紹介されている、こちらの本。
気になった方は、ぜひ読んでみてくださいね!
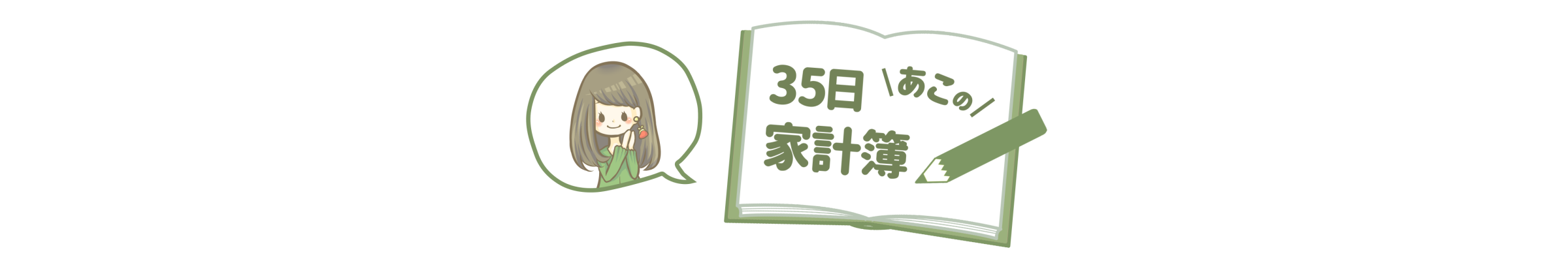
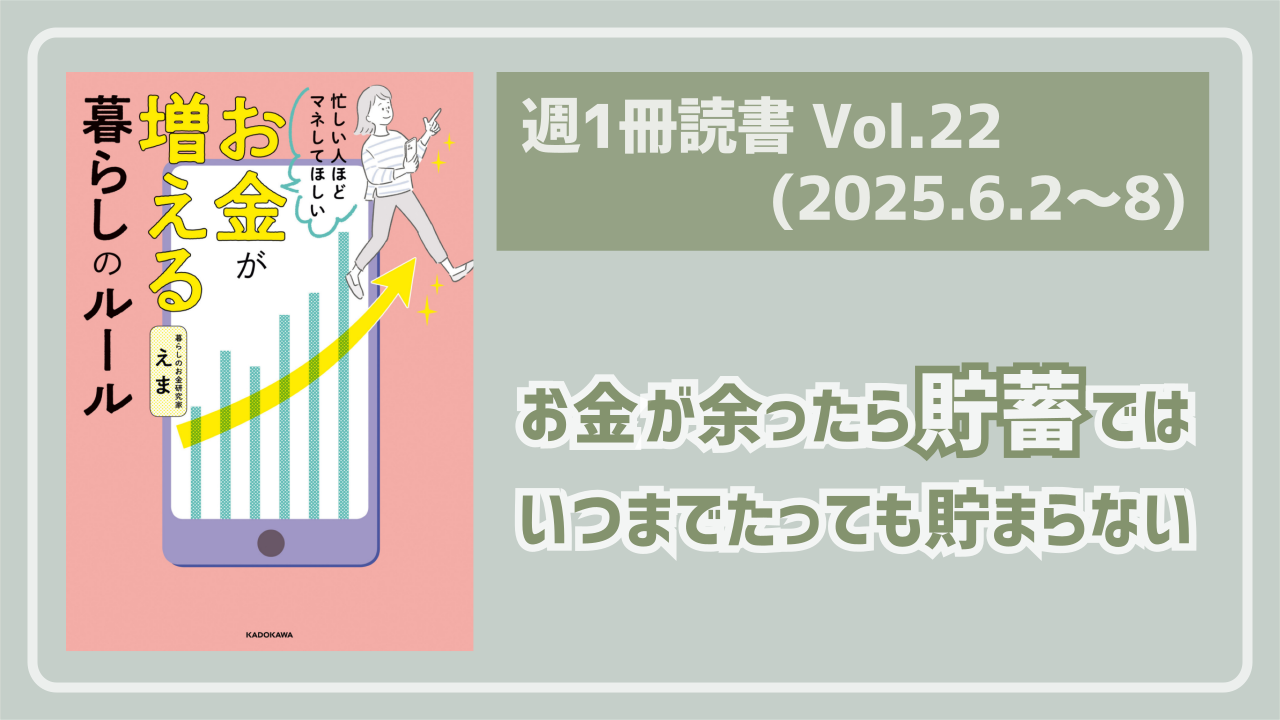


コメント